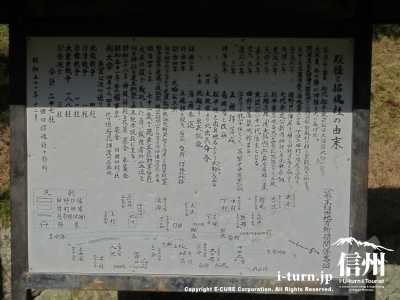龍岡城は、長野県佐久市にある近代城郭跡で、昔は龍岡藩の藩庁が置かれていた場所です。
築城時の堀仕様が稜堡式築城法を使ったため、いわゆる函館と同じ、五稜郭となりました。
函館五稜郭址が四年前完成しており、日本の城址でただ二つの貴重な洋式城郭となっています。
国指定の史跡で、現在城跡には佐久市立田口小学校があります。
五稜郭の堀の内部には神社もありお参りをすることもできます。
住所:長野県佐久市田口2981
電話:0267-82-0230
[googlemap lat=”36.19590612769248″ lng=”138.50146293640137″ align=”undefined” width=”575px” height=”300px” zoom=”13″ type=”G_NORMAL_MAP”]長野県佐久市田口2981[/googlemap]
龍岡城五稜郭の看板
日本に二つ龍岡城五稜郭。
函館と佐久にしかないという訳です。
五稜郭の堀
キレイな石垣が残っています。
堀には桜が植えられており春には桜の名所となるそうです。
龍岡城五稜郭の大手門
メインの入口は橋がかけられています。
ここで記念写真を撮っている方がいました。
大給 恒(おぎゅう ゆずる)は、三河奥殿藩の第8代藩主。のちに信濃田野口藩(竜岡藩)の藩主。奥殿藩大給松平家10代。江戸幕府の老中、若年寄。明治時代の政治家・伯爵。日本赤十字社の創設者の一人として知られる。旧名は松平 乗謨(まつだいら のりかた)。Wikipediaより
しかし読めない・・・
昭和九年に文部省によって掲げられたもので、これ自体が歴史になってしまいそうです。
説明書き
この五稜郭は幕末の動乱の時期に作られたということです。
坂本竜馬が死亡した、慶応三年に竣工されているので最近と言えば最近の感じもします。
ちなみに総工費4万円ということです。
五稜郭の平面図
右上のブルーの無い場所は現在、堀として水の無い部分です。
城跡は佐久市立田口小学校です。
大手門から入ると、グランド側に出ます。
堀のある小学校とはある意味、安全な気がします。
これは、小学校卒業生の贈り物
昭和44年の卒業生で、標高と緯度経度が示してありました。
殿様と招魂社の由来について
非常に難しい内容が書かれました、由来なのか沿革なのか難しいです。
ぜひ、現地でご覧になってください。
拝殿の内部
神社自体は無人ですが、かなり片付いており、普段から使われている感じがします。
トイレ
花見の時期は賑わいそうですね。
普段は使われていない感じです。
現在は堀の一部は道路
堀のなくなった部分も石垣を直してました。
日本で2つしかない五稜郭です、「函館まで行けない」「函館出身だ!」というはぜひ佐久の五稜郭を見学してみてください。